新潮文庫 『きもの』
著者:幸田 文
新潮社発行 平成8年12月1日
この本を読んで、とても印象的な一節がありました。
女はみんな、いつ、どんな思いで、着物を着たりこしらえたりしてるか、はたからわかりはしないよ。あたしにはおかあさんがそのセルをこしらえた時の、あのかあっと弾んだ気持ちがよくわかるよ。(幸田文『きもの』より)
現代ではあまり耳にしなくなった“こしらえる”という言葉ですが
この響きには不思議なノスタルジーが感じられます。
単に「用意する」や「買う」ではなく
「作る」でもない。
布を選び、色を決めて染め、時には自分で縫う――
そんな丁寧な過程を含んでいたからこその
「こしらえる」だったのではないでしょうか。
今の私たちが着物を求めるときは既製品を買うことが多いですが
昔はもっと「自分で作るもの」だったということでしょう。
自分で織ることも
いまよりずっと身近だったようです。
布を織り、染め、仕立てる。
その一連の流れは
現代よりずっと生活に根差していて
日常の一部として衣を整えたり仕立てたりという
手間と時間の積み重ねがありました。
だからこそ「こしらえる」という言葉が使われたのでしょう。
この言葉に触れると
母や祖母の世代の着物の支度を思い出すような懐かしさがあり
着物を通じて生活そのものを整える感覚を肌で感じる気がします。

この紬は私が自分のお給料で初めて作ったものです。
仕立ててから25年経ったいまも毎年袖を通し、大切に着用しています。
お正月のセールで見つけて一目で気に入り購入したのですが
あのときの高揚感は本当に忘れられません。
まさに“かあっと弾んだ持ち”でした。
「こしらえた」と表現することはできないのですが…
自分の手の中で作り上げたという感覚がないからでしょうね。
これが自分で縫ったのだったらまた別なのかもしれません。
その一方で、“買った”という表現ではすまない思いもあるのです。
呉服店のおかみさんとのやりとりや帯あわせのアドバイス
更にはそのときのお店にただよっていたお香のにおいまで
今でも昨日のことのようにまざまざと思い出すことができるのですから。
こんなことは洋服だと起こらないのですよねぇ。
まるで日本の女性のDNAに刻みこまれているのではないかと思われるほどの
ほとんど執念みたいな高揚感でした。

私はきものを購入して仕立てることを
これからも“作る”と表現すると思いますし
「こしらえる」と表現することはないと思うのだけれど。
いつか自分の手で作り出したという実感みたいなものを得たいという
訳の分からない欲求みたいなものはあるのです。
手仕事への憧れみたいな…
これもDNAなのでしょうか?
いま脳裏にやせ細った鶴が
機に自分の羽を打ち込んでいる図が浮かんできました(笑)
ああ、機を織ってみたい…
なんだか収拾のつかない話になってきました。
着物を「こしらえる」という言葉の響きには
私たちの心のどこか深いところを揺さぶる力があるようです。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/14aa8372.57f98814.14aa8373.63ef76ca/?me_id=1213310&item_id=10604304&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6082%2F9784101116082.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


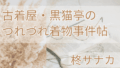
コメント